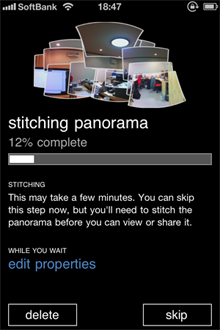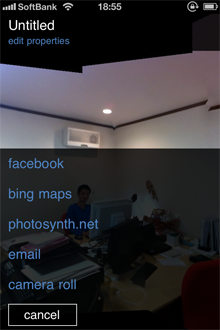バーチャルツアーはiPadと相性が良い
PanoPlazaで作るバーチャルツアーやバーチャルショップは、基本的にPC、iPhone、iPad、Androidタブレットでそれぞれ閲覧することができます。必要があれば、PCとiPhoneで画面表示を変えたり、機能を変えたりすることもたまにやります。そして納品時にお客様から頂くコメントの中で一番多いのは、「iPadだと気持ちよく動くねぇ」「タブレットの方が、直感的に楽しめるね」というものです。360度パノラマのコンテンツは、タッチで視点を操作したり、ビンチで拡大するなど、タブレットの操作と非常に相性が良いというのが、私たちと多くのお客様の共通した認識です。


※ICT総研:2012年4月26日
上記のグラフは、2010年度以降のタブレット端末の日本国内および世界での出荷台数です(2012年度以降は予測値)。iPadを筆頭に、タブレット端末は今や私たちの生活に広く浸透し、程なく日々の生活に欠かせないデバイスとなるかもしれません。自然と、「iPadで何をするか!?」「どんなコンテンツをiPadに載せるか」ということが話題になります。PanoPlazaでも、バーチャルツアーをアプリに埋め込んだり、iBooks形式の電子書籍に埋め込んだり、タブレットを絡めたお仕事を頂くことが多くなりました。慶應義塾大学様・国際航業株式会社様とご一緒させて頂いた「屋内混雑度共有アプリ:aitetter」では、二子玉川ライズ内の混雑度をAndroidから確認できる機能に加え、その場所の様子をパノラマで確認できるようバーチャルツアーを閲覧できるようにしました。Pihana Consulting様と一緒に三越伊勢丹株式会社様にご提案させて頂いた「イセタンハネダストア バーチャルショップ」では、伊勢丹様店舗に設置したAndroid端末の専用アプリ内に、バーチャルツアーを入れました。最近では住宅メーカー様向けに、モデルハウスをバーチャルツアー化し、電子住宅カタログの中で活用するというご提案をしています。最近では、360度パノラマ、バーチャルツアーの打ち合わせをしていると、「iPad」や「タブレット」という単語が必ず出てくるようになりました。
iBooks:作りやすさや配布のしやすさが魅力

バーチャルツアーと、iPadやタブレットという切り口で、PanoPlazaが注目しているのはiBooksです。360度パノラマ写真やバーチャルツアーを、スマホやタブレットで閲覧するには、色々な方法があると思います。アプリとして作りこんでもよいし、ブラウザベースで閲覧できるようにしてもよいし、AndroidであればFLASHで作ることもできます。現在様々な形式のものがありますが、電子書籍として公開することもできます。ただ私たちは、色々なやり方がある中でも、iBooksコンテンツとしてバーチャルツアーをiPadで活用することをお勧めしています。その理由は、iBooksの作りやすさと配布のしやすさ、それから前段で少し触れたiPadのシェアです。iBooksコンテンツは、アップルのAPP STOREでダウンロード可能な「iBooks Author」というソフトを使って制作します。ドラッグアンドドロップなどの直感的な操作で、電子書籍を制作編集することができます。そしてこの「iBooks Author」には、Webの標準的な技術で作られたコンテンツを、ウィジェットとして組み込むことができます。既に制作しているバーチャルツアーをウィジェット化するだけなので、iBooks用に追加の開発や余分な手間がかかることがありません。そういうわけなので、バーチャルツアーをタブレットで見るには、iPad(iBooks)で見るのが一番早くてお手軽ですよ、とお話させて頂いております。
iBooksや電子書籍への期待値は?

さて、ここまではどちらかというと、360度パノラマのバーチャルツアーを制作しているPanoPlazaスタッフとしての見解でして、実際に電子書籍やiBooksは昨今の世の中的にどうなのでしょうか。iBooksは、発表当初はとても話題になり、日本でも富士重工様の「LEGACY」のプロモーションで制作された事例(右)のように、スタイリッシュなコンテンツも登場してきました。すぐに浸透するものと感じていましたが、現時点でそれほど大きな広がりを見せているわけではなさそうです。一方米国ではそれなりに多くのコンテンツが流通しているようでした。iTunes Storeの設定を「US」にしてしてみると、膨大な数の電子書籍が出てきます。その中で、iBooks Authorによって作られた書籍には、「Made with iBooks Author」という印がついています。iBooks Authorによって作られた書籍は、iPad用、iPhone用でそれぞれ4万件を超えるくらいでした。これが多いのか少ないのか、今後の普及を期待するのに充分な数値なのか、現時点では判断できませんが、今後日本も含めてiBooksのコンテンツがより広く流通するようになる余地は充分あると予測しています。
iPad(iBooks)+バーチャルツアーは、これから!?

※APP BANK:2012年3月28日
一方、こんなデータもあります。上記はiPadユーザーの年齢と性別の分布です。これを見ると、iPadのユーザーは、割と年齢層が高いことがわかります。なんと40代以上のユーザーが、全体の50%を占めています。さらにユーザーの80%が男性であることがわかります。iPhoneやスマートフォンが、若者世代を中心に普及しているのに対して、iPadやタブレットは「大人向け」の渋いデバイスだということが分かります。

また、右の図は、そのiPadユーザーに聞いた「電子書籍を読んだことはありますか?」という調査の結果です。80%以上の人が、「電子書籍を読んだ事がある」と回答しており、90%の人が「電子書籍に興味がある」と回答しています。iPadやタブレット端末が広く普及していくと同時に、「電子書籍」という言葉も広く認知され、多くの人が「電子書籍」に興味を持ち「読んでみたい」と考えていることが分かります。「これからは電子書籍が来る!」と思いたいところなのですが、そういったソフトウェア会社、制作プロダクションの気持ちに水を差すようなデータもあります。

※MMD研究所:2011年11月25日
上記のグラフは、「今後増えたらいいと思う電子書籍のジャンル」についての調査結果です。これを見ると、「電子書籍」はあくまで「紙の書籍」の延長線上であり、まだまだその枠を超えたコンテンツとして認知されていないように見えます。「Webコンテンツをウィジェットとして電子書籍に埋め込む」ことで実現できる、インタラクティブなコンテンツ、リッチコンテンツ、ネットワークと連携したコンテンツという意味では、「期待が薄い」というよりは「それが比較的簡単にできることが、充分に知られていない」状況なのかもしれません。充分に知られていないということは、事例や実績が増えれば、iBooksの活用について認知が広がり、あたらしい機会が生まれてくる可能性がある、ということかもしれません。(という風にとらえたい)
今日は、360度パノラマ写真、バーチャルツアー、iPad、iBooksというキーワードで、少し前にPanoPlazaスタッフ内で議論した内容をもとに、ブログを書いてみました。バーチャルツアーをどのように活用するかという話は、お客様それぞれで最適な形があり、PanoPlazaではどのような開発手法、制作方法でもご提案させて頂く事ができます。一方で、低コストで、スピーディに再利用、活用するための手法として、iPad(iBooks)周りの今後の動きにも注目していきたいと思います。
長くなりましたが…、最後までお付き合い頂きましてありがとうございました! iPadやiBooksのネタについては、今後も継続的に書いて行きたいと思います。